|
「ボルタの電池は何となくわかるんですが、備長炭というのは意外ですね」
湯本:これは、サイエンスプロデューサーの米村伝次郎先生が考案したものなんですね。米村先生とは、「科学」の本誌の編集の時代からずーっといろんな実験ページを作ってきまして、そういう関係でこのネタを使わせていただきました。
「でもどうして備長炭が電池になるんですか?」
湯本:それは、備長炭には、数ミクロン~数百ミクロンという小さな穴がたくさん空いてるからなんですよ。この穴のおかげで、わずか1グラムの備長炭の表面積は、約300平方メートルにもなるんですよ。この穴が、電子をより頻繁に活動させるのに役に立つんですね。そのために、強力な電池になるんですね。
「では備長炭でないとだめなんですね」
湯本:普通の炭でも弱い電池にはなりますが、備長炭の足元にも及ばないですね。備長炭を使うと、0.7ボルト、130ミリアンペアくらいの電池になるんですね。だから、これを直列に2つつなぐと、単三乾電池1本で動くラジオくらいなら聞けますね。
金子:このセットには、活性炭の電池を作るキットもついてますが、これも0.7ボルト、50~60ミリアンペア程度の電池になります。なので、備長炭電池と活性炭電池をつなぐと1.5ボルト近い電池にすることができますね。 |
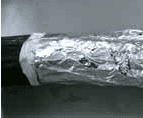
▲アルミを巻いた備長炭。直列につなぐとラジオが聞けるほどの電池になる |
「ボルタの電池はどれくらいの電圧、電流がでるんですか?」
湯本:これも電圧が0.7ボルトは出るんですが、電流は15ミリアンペア程度しか出ないんです。なので、これを乾電池のかわりにするのはちょっときついですね。
金子:でも、オキシドールや酸素系漂白剤を入れるとかなりパワーアップします。
湯本:これは、プラス極の銅板の表面に水素の泡が付着して、すぐに効率が落ちるんですね。オキシドールや酸素系漂白剤を入れると、この水素を除去してくれるんですね。これで効率が一気に上がるんですよ。
金子:これで、ボルタの電池でも普通のモーターくらいまではいけますね。太陽電池用の弱い電流で回るモーターじゃなく、ごく普通のモーターが回りますよ。
「では、これで電池の原理を体験できますね」
湯本:そうですね。備長炭電池は、アルミホイルで備長炭をくるんで実験するんですが、やっているとアルミホイルがだんだんぼろぼろになっていくんですよ。実際に目で見えてるわけではないんですが、「あー、アルミホイルが電子になって移動してるんだな~」って感じが本当にするんですよ。子供の頃、よく電池を分解したりしたじゃないですか。それより、はるかに目の前の変化で感動できること、保障つきですね。 |

▲備長炭に巻いて電池を通した後のアルミは、穴が空いてボロボロに… |
「ありがとうございました」
|